
『☆こけし、風鈴、アルマイト☆』懐かしのレトログッズ7選紹介!(その2)レトログッズの名前や由来など。
「懐かしい〜そういやそんなモノあったなぁ〜」
今では見ることのない、でも見ると感慨深くなる。そんな懐かしのレトログッズありますよね。
今回はそんなレトログッズを紹介、及び豆知識を7選集めましたので解説していきたいと思います。
その1に関しては【↓下のリンク↓】からご覧になれますので、読んでない方はぜひ見ていってください。
目次
Toggle懐かしのレトログッズ7選

がま口財布
金属の留め具がパチンと閉じる、レトロで実用的な古銭入れ。留め具部分は口金(くちがね)と呼ばれています。
日本でも古くから親しまれており、和風のファッションとしても人気があります。
がまは蛙(がまがえる)に由来します。口の開閉が似ていることから名前がついたそうです。
現在でも「がま口職人」は日本各地にいて、手作業で一つ一つ丁寧に作られているそうです。
風鈴
風を受けて音を鳴らす吊り下げ式の道具。音色は風鈴の素材によって異なります。
日本では音を楽しむだけでなく「魔除け」「涼感」としても使用されてきました。
お椀の部分を「鐘」、中にあるおもりを「舌(ぜつ)」、下の紙を「短冊」といい、短冊が風をキャッチし舌が鐘にあたることで音を鳴らします。

風鈴の由来
今から約2000年前。中国に「占風鐸(せんぷうたく)」と呼ばれる占いが存在していました。
竹林の東西南北に青銅でできた風鈴(風鐸)をぶら下げておき、風向きや音色によって吉凶を占うのです。
風鐸は日本に仏教が伝来するのと同時に、遣唐使たちによって日本に伝わったと言われています。現在でも寺の屋根や塔の軒の四すみにぶらさがっているのを見ることができます。
平安から鎌倉時代にかけては、貴族達に魔除けとして使われていたそうだとか。
ちなみに初めて風鈴という名称を使ったのは浄土宗の「法然」だと言われています。

屋根に吊るされた風鐸

アルマイト食器
昭和中頃から平成初期にかけて、学校給食、家庭、キャンプ用など幅広く使われた食器。
アルマイトとはアルミニウムの表面に酸化アルミニウムの膜をくっつける処理のことです。
錆びにくく、銀色で艶があり、軽くて割れないなどの特徴があります。
おひつ
炊けたご飯を一時的に移し替え保管しておくための道具。
電気炊飯器が普及する前は多くの家庭や旅館などで使われていました。
蓋の種類によって「つめびつ」「のせびつ」「かぶせびつ」などの種類があるそうです。
「飯櫃(めしびつ)」とも呼ばれるそうだとか。


こけし
日本の東北地方発祥の伝統的な木製人形。シンプルで温かみのある形と、素朴な表情が特徴的です。
形や模様により分類分けされており、現在約11種類の分類が確認されているそうです。
近年では、ポケモンこけしやエヴァンゲリオンこけしなど、有名どころとコラボしたこけしも存在しており、外国人の方からも日本のお土産として認知されてきているのだとか。
こけしの歴史
こけしが誕生したのは江戸時代の末期、東北地方に住む木地師(きじし)と呼ばれる木製のお椀やお盆作りを生業としていた職人たちによって生み出されたと言われています。彼らは余った木や素材を使い、温泉地などで子供用のお土産品としてこけしをつくっていました。
こけしの名前の由来は諸説あります。木で作られたから「きでこ」と呼ばれたり、芥子人形(江戸時代に流行したとても小さい人形)を由来とした「こけず」。
他にも様々な名称があったため、1940年、こけし工人(現代でこけしをつくっている職人)やその関係者が集まり、正式名称を「こけし」に統一しました。

陳列されたこけし
防犯ブザー
危険を感じた時、大きな音を鳴らして周囲に助けを求める小型の警報装置。
1960年代、痴漢や強盗対策のため、女性向けに販売されていました。
電車のアナウンスが90dB(デシベル)、工場の騒音が100dB、に対し一般的な防犯ブザーの音の大きさは110〜130dBなんだとか。


おろし金
金属やセラミックの素材で作られた、食材を細かくすりおろすための調理器具。
平たい板状の表面には多数のギザギザした突起が並んでおり、スライサーとセットになったおろし金も販売されています。
現在では工業製品が主流ですが、職人手作りの銅製おろし金なども存在しており、根強い人気をほこっているそうです。
あとがき
いかがだったでしょうか?
他にも、いろんな記事をまとめてますのでぜひご覧になってください。


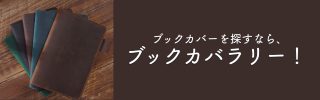





コメントを残す